電気設備の健全性を一瞬で数値化できる指標、それが 絶縁抵抗 です。「導体どうし」「導体と大地」の間にどれだけ電流が漏れにくいかを表し、数値が高いほど安全度が高いというものです。
絶縁抵抗とは
電気は決められた導線の上を流れてこそ役に立つものですが、古いコードのひび割れや湿気を帯びた配線を通じて回路外部に逸れてしまうことがあります。絶縁抵抗は、この回路と外部を断絶するための抵抗を絶縁抵抗といいます。この抵抗値が大きければ大きいほど外部に電気は流れることはありません。
オームの法則より
\(V=I×R\)
で抵抗の値を求めることができます。同様に絶縁抵抗についてもこの式で求めることができます。
ここで、Vは電圧、Iは流れた電流、Rが抵抗です。式を見ればわかるように、同じ電圧 Vを印加したときに電流 Iが小さければ小さいほど、抵抗 Rは大きくなります。
絶縁抵抗の計測方法
絶縁抵抗を測るために測りたい使用機器の使用電圧の20~30%程増やした電圧をかけます。例えば、使用機器の使用電圧が100Vだった場合、120~130Vほどを機器に流し込みます。また、配線に流れる電流を1μAとすると、
\(R=\frac{V}{I}=\frac{120}{1×10^{-6}}=\)
このようにして絶縁抵抗を測定する機器を絶縁測定器(メガリング)といいます。
絶縁抵抗の大切さ
電気が横道にそれると具体的に何がまずいのでしょうか。ここで登場するのが ジュールの法則
\(P=I^2×R\)
です。
この式は「電流が流れるところには必ず熱が出る」こと、しかも熱の量 P は電流 I の2乗に比例して急激に増えることを教えてくれます。
たとえば漏れ電流が10mAから20mAに倍増しただけで、発熱量は4倍に跳ね上がります。配線にほんのわずかなキズが入って絶縁抵抗が下がり、そこへ湿気が加わって電流が少し増える。そんな小さな変化が、配線ビニルを軟らかくし、やがて炭化させ、最後には火花を生んで火災に至ります。
さらに電流が人体に流れ込むと状況は深刻です。人間は、1 mA程度でもビリッと刺激を覚え、10mA で筋肉がけいれんし、100mAを超えると心室細動の危険が出てきます。絶縁抵抗は、この危険領域に入らないよう電流をμA(マイクロアンペア)レベルに抑えるバリアとして機能しているのです。

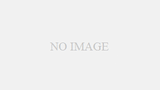
コメント